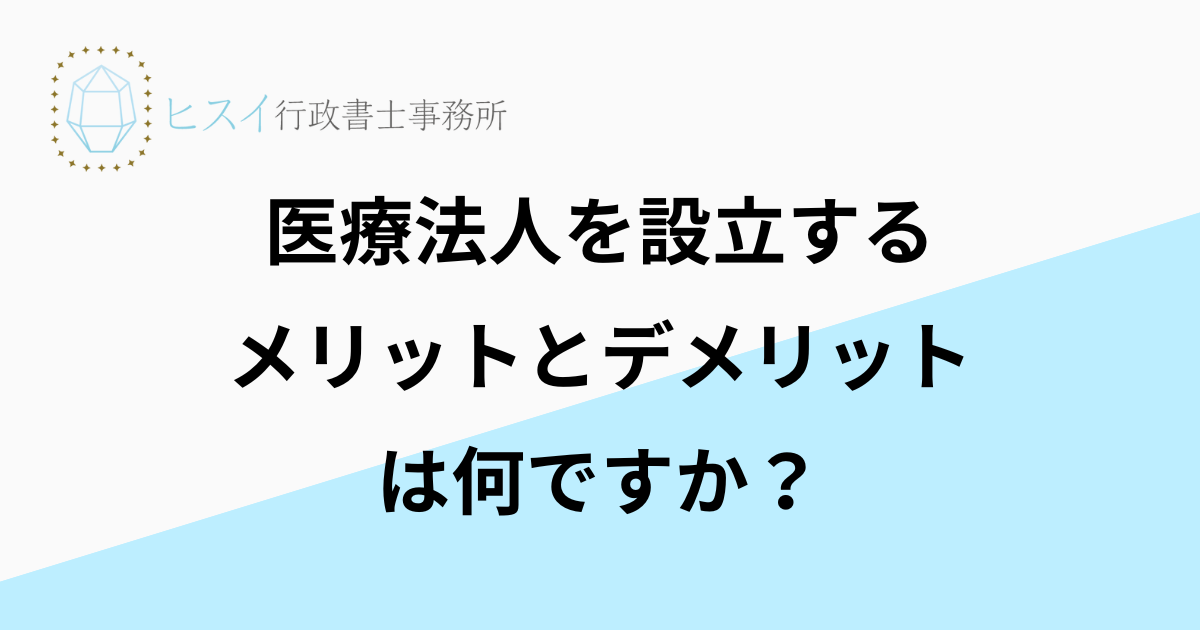医療法人の設立について関心を持つ医師や歯科医師の方は多く、特に個人でクリニックを経営している方にとっては「法人化すべきかどうか」は大きな判断ポイントです。節税や事業承継の面で有利とされる一方で、設立後の制限や手続きの煩雑さがあるため、慎重な検討が求められます。
ここでは、医療法人を設立することのメリットとデメリットを整理し、制度の背景や注意点をわかりやすく解説します。
医療法人設立のメリットは何か?
医療法人を設立することで得られる主なメリットは以下のとおりです。
- 節税効果が期待できる
個人事業としての所得は最高税率55%(所得税+住民税)に達することもありますが、法人化することで法人税率(中小法人で約23.2%)が適用され、税負担が軽減される場合があります。また、給与所得控除を活用して家族を役員にすることも可能で、所得の分散による節税も可能です。 - 事業承継がしやすい
個人診療所の場合、開設者が死亡すれば廃止届が必要ですが、法人であれば法人格が残るため、事業を継続しやすくなります。家族や親族に医療機関を継承する計画がある場合、医療法人化は有力な選択肢です。 - 資金調達がしやすくなる
医療法人は法人格を持つため、金融機関からの信用が高まり、融資を受けやすくなります。また、大規模な設備投資や分院展開を考える場合には有利です。 - 福利厚生の充実が可能
法人化により、退職金制度や社会保険制度を整備しやすくなります。従業員の採用・定着にもプラスに働きます。
医療法人設立のデメリットとは?
一方で、医療法人化には以下のようなデメリットもあります。
- 設立手続きが煩雑
医療法人の設立には、都道府県の認可が必要であり、設立時期も年2回程度に限定されています。事前協議や書類の準備に時間と労力がかかるのが実情です。 - 収益の私的流用が制限される
医療法人の利益は、法人に帰属します。個人の自由に使うことができず、配当も禁止されています。そのため、法人の資産を私的に活用することはできません。 - 事業の自由度が低い
医療法人は「非営利性」が原則とされており、行える事業内容に制限があります。例えば、美容医療などの自由診療についても、自治体によって解釈が異なることがあります。 - 解散が容易でない
一度設立すると、解散する際には厳格な手続きと認可が必要となり、解散後の残余財産も国や地方公共団体等へ帰属します。個人への分配はできません。
よくある誤解とその真実
「法人化すれば必ず節税になる」と考える方もいますが、収益が一定以上でないと逆に税負担が増えることもあります。また、「医療法人になれば自由診療が自由にできる」との誤解もありますが、あくまで公益性が重視されるため、注意が必要です。
実務上の注意点と落とし穴
設立時には、都道府県との事前協議や事業計画の立案、定款の作成など複雑な手続きが求められます。また、設立後も毎年の事業報告や2年毎の役員変更の届出が義務づけられており、法人運営に慣れないと負担が大きくなる可能性があります。
税務や労務管理も個人診療所と比べて複雑化するため、経理体制の整備や専門家の支援が不可欠です。
専門家による支援の重要性
行政書士や税理士、社会保険労務士などの専門家は、医療法人設立の手続きや法人運営の支援を行っています。行政書士は設立認可申請や定款作成を、税理士は法人税申告や節税アドバイスを、社労士は労務管理や社会保険の整備を担当します。
特に初めて法人化を検討する医師・歯科医師にとって、これらの専門家の支援を受けることで、手続きミスや将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ:医療法人設立は計画的に進めよう
医療法人の設立には明確なメリットがある一方で、運営や制度面での制約も多いため、十分な情報収集と計画的な準備が必要です。現在の収益状況や将来のビジョンに応じて、法人化が本当に適しているのかを見極めましょう。
気になる方は、早めに専門家に相談し、具体的なシミュレーションを通じて判断することをおすすめします。