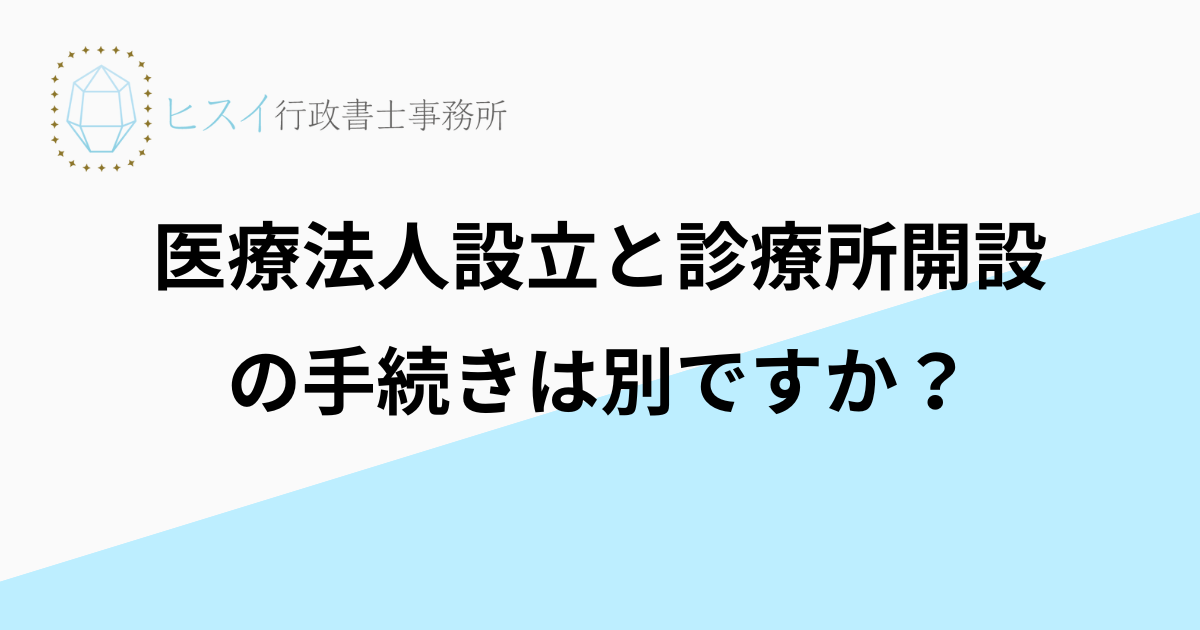医療法人設立と診療所開設の手続きは別?制度上の違いと注意点を解説
医療法人の設立や診療所の開設を検討している医師や医療従事者から、「医療法人の設立と診療所開設の手続きは別ですか?」という質問は非常に多く寄せられます。開業を目指す際、これらの手続きを混同してしまうと、準備不足や許可遅延につながる可能性もあります。
この記事では、医療法人と診療所それぞれの制度の違いや、手続き上の注意点をわかりやすく解説します。
目次
医療法人設立と診療所開設は別の手続き
結論から言うと、医療法人の設立と診療所の開設は「別の手続き」です。
医療法人の設立は、法人格を持った組織として医療事業を行うための手続きです。一方、診療所の開設は、具体的に医療行為を行う場所を運営するための手続きであり、法人・個人を問わず必要になります。
つまり、医療法人として診療所を開設する場合には、「①医療法人の設立認可」と「②診療所開設の許可や届出」の両方が必要です。手続きの目的や根拠法令も異なります。
制度の違いと手続きの流れを解説
医療法人設立の手続きは、医療法に基づき、都道府県知事の認可を受ける必要があります。各都道府県により異なりますが、例として東京都は年2回の受付期間があり、事前協議・申請書類の作成・審査・認可まで数か月を要します。
診療所開設の手続きは、医師法および医療法に基づき、施設の構造や人員配置を満たしたうえで、開設場所の所轄保健所に「開設届(または許可申請)」を提出します。医療法人が運営主体となる場合は、法人設立認可後でなければ開設届を提出できない点にも注意が必要です。
具体的には、次のような流れとなります:
- 医療法人設立の準備(社員・定款・役員構成の検討等)
- 都道府県への設立認可申請(事前協議含む)
- 医療法人設立の認可・登記
- 診療所物件の整備・設備導入
- 保健所への開設届出・立入検査
- 診療所の開設(保険医療機関指定の申請など)
よくある誤解:法人設立=開設と考えてしまう
「診療所を開設する=法人化しなければならない」と誤解されがちですが、診療所は個人名義でも開設可能です。医師1名で小規模に開業する場合、まずは個人で開設し、後に医療法人化するケースが多くあります。
また、医療法人を設立しただけでは診療所は開業できません。診療所の開設には別途、施設の基準を満たしたうえで保健所に届出を行う必要があります。
実務での注意点:スケジュール管理と申請漏れに注意
医療法人設立と診療所開設は、それぞれ別個の手続きでありながら、開業スケジュールの中では密接に関係しています。特に医療法人としての開業を予定している場合、法人設立の認可時期が診療所開設に影響するため、全体のスケジュール管理が重要です。
また、法人設立後の登記や医療機関コードの取得、保険医療機関指定の手続きなども連動しており、各工程に必要な書類やタイミングを誤ると開業が遅れることがあります。
士業による支援内容:行政書士・社労士・税理士の役割
医療法人設立や診療所開設の手続きは、専門的な書類作成や法令知識を必要とするため、行政書士などの士業による支援が有効です。
- 行政書士:医療法人設立認可の書類作成や申請手続き、事前協議対応、診療所開設届出書類の整備など
- 社会保険労務士:スタッフ雇用に伴う社会保険の手続き、労務管理体制の整備
- 税理士:医療法人の会計処理、税務申告、法人化による節税アドバイス
複雑な手続きを確実かつスムーズに進めるためには、こうした専門家と連携しながら準備を進めることが望ましいでしょう。
まとめ:別手続きであることを前提に早めの準備を
医療法人設立と診療所開設は、制度上も手続き上も別個の手続きであり、それぞれに異なる準備や申請が必要です。とくに医療法人としての開業を目指す場合、スケジュールや必要書類の管理を怠ると、開業時期が遅れかねません。
開業に向けての一歩を踏み出す際には、専門家のサポートを受けながら、正しい順序で確実に手続きを進めることが成功のカギとなります。